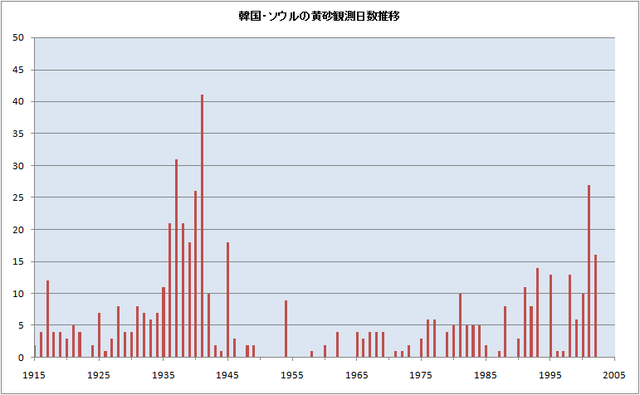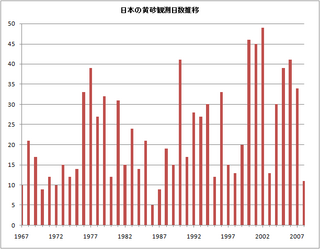紅門
反清秘密結社/フリー百科事典ウィキペディア
紅門はもともと天地会と呼ばれていましたが、後に紅門会として知られるようになりました。清朝の主要な秘密結社で、主に中国南部で活動し、福建省、広東省、湖広市などの地域でより繁栄しました。歴史家は、青鋼などの反清の秘密結社をすべて表すために「紅門」という用語を呼ぶことがあります。その後、さまざまな名前を持つ複数の地下社会や政党に発展し、華僑が東南アジアに移住するにつれて東南アジアに広がりました。


清朝末期、戴君連の革命党は満州族の清朝を打倒するために紅門運動に参加した。 1911年の中華民国の建国後、天帝会と三合会のメンバーの多くが中華人民共和国の地位を獲得した。国民革命軍。 1949 年以降、香港の三合会組織の 2 人の指導的ボスである葛兆皇と項祥は、どちらも中華民国陸軍の階級を持っていました。
ソース
紅門の起源については、鄭成功と陳晋南が創始した説、方儀之が創始した説、康熙嘉陰説、雍正嘉陰説、万雲龍が紀元前に創始した説など、十数の説がある。乾隆26年、雍正治の初期に英雄たちが天地協会を再設立したという説、その他多くの説がある。
グループ名
漢代、紅門、天帝会の伝説
陶承章の著書「教会の起源に関する研究」[2]には、「崇高な理想を持ち慈悲深い人々が中原の荒廃に耐えられず、祖国を取り戻すために秘密結社を結成した」と述べられている。 、そして紅門会議が設立されました。 紅門とは何ですか?明の時代の太祖が統治名であったため、名前が付けられました。 それを始めたのは鄭成功であり、それをフォローして修正したのは鄭成功です。 「一人は天を父として崇め、二人は地を母として崇める」[ 3]ので、これが省略されています。「天の父と地の母」は清王朝と戦い、明王朝を再興することを誓った、それで彼らは「天地協会」と呼ばれました。
5つの舵
紅門への暗示
紅門の秘密コード
- 「私は天を父として崇拝し、地を母として崇拝します。」
- 切り込みは「Yi Xin Fu Da Ming」の反対の「Ming Da Fu Xin Yi」です。
- 決して口から離れず、決して手を離れないでください。
- ムリは世界と戦い、シュンティアンのルールと契約を知っています。
- 5人は別れて詩を書きましたが、誰もホン・インのことを知りませんでした。この出来事は兄弟全員に伝わり、後に再会しました。
主枝
格老匯
曽国帆が太平天国を破った後、清朝が不審に思うのではないかと懸念し、一部の湖南軍が長江海軍に再編され、多くの人々が反戦隊に加わった。清天帝会は湖南省と蜀市でパーティーを開催し、レンジャーズ・グリーン・フォレストとして知られていました。同胞団のメンバーの中には、詐欺、誘拐、賭博、売春宿、強盗、アヘン密売などに関わった者もいた。劉坤は両江省と広東省の総督を務めていた間、治安を正し、広東省と広西チワン族自治区の総督だったとき、ギャンブルは悪であると信じ、1892年にギャンブルを禁止した。彼は両江の葛老会を排除した。湖南軍の「葛老会」 はさらに「潘氏」、別名「潘家」などに分かれた。
トライアド
「トライアド」とは、「天と地」に「人」が参加するという3つの才能の統一を表しており、実は「天帝会」のメンバーのコードネームである。
三合会は天帝会の名前の変更または支部であり、嘉慶 16 年 (1811 年) には、葛老会よりも早くに登場しました。三合会の内容と性質は天地協会と全く同じです。 1840 年のアヘン戦争の前後、広州、仏山、肇慶での三合会の活動がより頻繁になりました。道光末期から咸豊時代にかけて、広東省と広西チワン族自治区では党と人民による反乱が絶えなかった。広東三合会は清朝に対する「ホンビン」蜂起に参加した。咸豊の治世 4 年 (1854 年)、さまざまな三合会が仏山と肇慶で反乱を起こし、まず広州を占領しようとしました。広東省と広西チワン族自治区の知事葉明チェンは三合会のメンバーを虐殺した。多くのトライアドは香港、東南アジア、アメリカに移住しました。 1857 年に広州がイギリス軍とフランス軍に占領された後、貴族や近隣の町の人々が団連公局を再建し、仏山に総局が設立されました。その後、一部の集団訓練は三合会の影響を受けて次々と紅門集団となった。
清末には三合会などが積極的に革命に参加し、孫文、黄興、陶承章、楊曲雲、鄭世良、陳其美らが入党した。現代中国本土の中国志功党は、現代天地協会の海外支部である志功党から発展しました。 20世紀初頭に米国で設立されました。
現代では、一部のトライアドはトライアド組織に変わっており、香港ではトライアドのメンバーであることを公表すると刑事罰を受ける可能性があります。
ジー・ゴン・タン
Zhi Gong Tang はもともと「Hong Shun Tang」と呼ばれ、1848 年にサンフランシスコで創業されました。 1898年、サンフランシスコ市庁舎に「非営利」公共福祉団体のライセンスを登録する際、清の大臣からの抗議を避けるために名前をZhi Gong Tangに変更した。 Zhi Gong Tang の主な職務責任は、鉄道労働者と金鉱山労働者の生活権を守ることです。その結果、組織は 60 年以内に急速に拡大し、鉄道沿線に発展し、南北アメリカの主要都市に支部を設立しました。アメリカの鉄道路線は東海岸と西海岸から同時に建設されたため、ニューヨークのチークンホールはその「本店」です。
ファン・サンデは当時、サンフランシスコの志功教会の指導者であり、メキシコと南米の2つの支部教会の指導者も務めました。指導者の役割は、本教会の管理上の方向性と政治について連絡し、情報を提供することですが、分教会の内政には干渉しません。 1903年、孫文は長兄の孫梅に加わるためにホノルルへ行き、資金集めと知名度を上げようとしたが、象山(中山)出身の子立は、彼が清の宮廷の囚人であり、彼の立場を理由に、ほとんど彼を無視した。仕事は何も進まなかったので、彼はアメリカ大陸で発展したいと考えました。しかし、アメリカは清朝と国交があり、アメリカの主要都市では「王党派協会」が活動していた。したがって、私たちは軽率な行動をするつもりはありません。
孫梅と黄三徳は旧知の仲で、孫文のアメリカでの発展を助けるために黄三徳に手紙を書いてアドバイスを求めた。紅門組織は南北アメリカ全土に広がっていたため、孫文を守ることができるのは紅門だけだった。唯一の条件は、孫文が紅門の会員であること。孫文の反清の野望とホンメンと同じ目的を考慮して、ホノルル「国家安全協会」の黄三徳の養叔父鍾水は、黄三徳自身が保証人となり、孫文に60人以上の会員を推薦した。それは、同じ家族の兄弟姉妹が将来お互いに敬意を持って挨拶できるようにするための「赤い棒」です。そのため、1904年5月に孫文がタンダオからサンフランシスコに到着した際、王立忠誠協会の通報により清朝の捕虜として税関に拘留された。法廷に行って初めて、彼はホンメンの規則に従い、全財産を使い果たし、裁判所の財産を担保にし、ワシントンの弁護士に「仲間の弟子」を救出するよう招待したのだが、17日後に孫文は釈放された。
1925 年 10 月 10 日、米国サンフランシスコで開催された五大陸紅門約束会議は、中国志功党の設立を決定しました。1925 年 10 月、中国志功党の第 1 回大会で陳敬明が党首相に選出されました。 。 12月、陳京明は香港に引退し、陳京明と唐継耀は主に中国本土に首相として選出された。中国志公党は中華人民共和国の設立に参加し、 1949 年以前は中国本土の8 つの民主政党の 1 つでした。
1946年7月、中国の上海で開催された五大陸紅門約束会議では、9月1日に紫都美堂と趙瑜を主席・副主席とする中国紅門民主党の設立が決定され、中央党本部が上海に置かれた。現在は主に海外で流通しています。
2010年5月21日、正式名称「紅門」を持つ最初の政党が中華民国台湾内務省に登録・設立された、中国紅門志功党(党証第167号)である。台湾の紅門の二番目の支部であり、「常に国の発展と人民の幸福を第一に考える」という目的に基づいており、シャオ・ミンインが率いています。台湾の紅門志功堂の館長である袁宝氏と、台湾高雄市のが正式に設立され、太陽を讃えられました。中華民国の建国の父である温(中山)氏が首相に、台湾の紅門志功堂の館長である蕭明英氏が会長に選出され、中国の紅門春宝山の指導者である李鳳山(鳳格)氏が選出された。グループは常任名誉会長に選出され、その本部も台湾の高雄市にあり、現在の党員は主に台湾および国内外に分布しています。
紅門の発展
東南アジア
清朝中期および後期には、紅門山塘支部は江南と中国全土に広がり、さらには東南アジア、ヨーロッパ、米国にまで発展し、数百万人の会員を抱えていました。清朝に対する粘り強い抵抗により、紅門回党は太平天国と1911 年の革命の重要な同盟者となりました。孫文、秋瑾、陶承章ら1911年の革命家たちは次々と紅門関連の組織に加わり、孫文氏は直接紅門を国民旧革命党、中国唯一の革命団体である天帝会と呼んだ。
清朝の弾圧下で、紅門社会党は海外開発組織に目を向け、常に新旧植民地主義の搾取と抑圧に抵抗する各国の中国人実業家や華僑の先頭に立って、憎悪と憎悪を呼び起こした。初期の西側植民地政権の注目。清朝の乾隆帝は紅門社党を撲滅するため、南東部の諸州を動員して紅門社の歴史を調査したが、それでも「決定的な証拠は無い」と感じていた。
紅門は清朝を打倒した革命に多大な貢献を果たし、1911年革命の指導者の一人である譚仁峰は「社会改善協会の意見」で次のように書いています。 200年前に植えられた「紅門党」 「運動の初期には、紅門兄弟だけが秘密を守ることができた。運動が始まった後は、どんなに遠くても、命令に従うことができたのは紅門兄弟だけだった。」近くの人々は、どんなに危険な状況であっても、誰もが勇敢に率先して行動し、武昌蜂起が起こり、地方はそれに応え、数か月以内に実際に共和国が完成しました。紅門兄弟の。」
台湾
紅門の革命的な性格とその神秘的な雰囲気のため、中華民国の中央政府が台湾に移転してから長い間、紅門は開かれた市民社会になることを申請することができませんでした。
戒厳令解除後、すべての紅門教会は1989年に「中華民国社会事業建設促進協会」という法人を設立し、対外交流を始めたが、当時は「紅門」という言葉は存在しなかった。公的に使用することが許可されています。
2004 年 1 月 11 日、紅門南華山教会は中華民国内務省に登録し、法人の地位を有する一般市民団体である「中華民国国際紅門協会」を設立しました。 。
中華民国内務省に登録されている紅門関連の政党には次のものがあります。
- 当初の名称は中国台湾志功党(党証書第098号)であったが、2017年12月16日に中国国民志功党に改名された。
- 2010年5月21日、正式名称「紅門」を持つ最初の政党が中華民国台湾内務省に登録・設立された、中国紅門志功党(党証第167号)である。Zhi Gong Tangの首席ホールマスターである台湾のホンメン・シャオ・ミンイン氏が公選され、その使命は「常に国の発展と人民の福祉を第一に考える」ことである。
- 中国清蓮党(党証書第 184 号)、紅門清蓮堂システムは、世界的に認められた清蓮堂教会首席指導者、ホン・ガン・何・ジュンユアン氏が議長を務めています。
- 中国新紅門党(政党証明書第200号)、台湾紅門共産党(政党証明書第262号)など
現在、台湾のほとんどの丘は葛老匯によって占められています。
中国本土

1925年10月10日、米国サンフランシスコで開催された五大陸紅門約束会議では、中国志功党の設立が決定された。 1925 年 10 月、中国自公党の第一回党大会は陳敬明を党首相に選出した。 1925年12月、陳京明は香港に引退し、中国志公党中央党本部が香港に設立され、陳京明と唐継耀が首相および副首相に選出された。
1949 年の中華人民共和国の設立後、中国志功党は中国共産党の多党政治参加政策に応え、中華人民共和国の 8 つの参加政党の 1 つとなりました。 2007 年 4 月、中国志功党中央委員会副主席の万剛氏は中華人民共和国科学技術大臣に任命され、第 13 代中国志功党中央委員会主席に就任しました。党に所属し、第11回中国人民政治協商会議全国委員会副委員長を務め、傅作儀の死後30年以上で初めて祖国に帰国した海外のホンメン華僑団体と接触した非中国共産党の閣僚となった。
他の紅門支部組織については、そのほとんどが現実逃避を追求しており、現在中国本土に存在する紅門支部のほとんどは、1911年革命時の紅門組織の名残であると言われている。
カナダ

1840 年以前には、北米に移民した中国人はほんのわずかでしたが、19 世紀半ばまでに中国人移民の数は急速に増加し、当時は数十万人の中国人移民がいたと推定されていました。そこには、太平天国の乱の将軍楊福清が反清蜂起が失敗した後、秘密結社を設立するために米国のサンフランシスコに亡命したという噂も含まれている。 20世紀までに、中国人移民は北米の主要都市に広がり、チャイナタウンを発展させ、サブカルチャーの「タン」(ギルドや官公庁)を組織した。サンフランシスコは、中国の秘密結社が最初に出現した都市であり、1882 年に設立されました(その他のより有名なギルドは次のとおりです)。
- Hip Sing Church : ニューヨークとその他 13 の州に支部。
- アン・リャン・タン:ニューヨーク。
- ビン・クン・トン:カリフォルニア州、ワシントン州。
- Cuishengtang : 米国のカリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州、カナダ。
- ホップシェン教会: カリフォルニア、オレゴン、ワシントン、アイダホ、コロラド。
他には謝益堂、金蘭事務所、翠英堂、英端堂、広徳堂などがあります。
他の
整理する
紅門組織の利点は、縦横の制度があることです。例えば、役職で言えば、指導者、座間、幹部、腹心、巡回といった縦割りの制度もあります。 「話し方」と「身振り」。たとえ初めて会ったとしても、ホンメン兄弟は、そのジェスチャーを見て、「春の暗号の隠された言語」を聞いて、「華亭の誓いの兄弟関係」と言った瞬間に、彼らは兄弟、つまり生死の友人です。元々の憎しみも翡翠の絹に変わった。この垂直方向と水平方向のシステム、専門用語、ジェスチャーはすべてホンメンの学識ある人々によって捏造されたものであり、世界中の他のどの秘密組織もこれに匹敵するものはありません。紅門組織は入会資格がなく、入会後はお互いに兄弟のように扱われるため、秘密組織でありながら台湾から中国本土、そして海外まで急速に発展しています。
ラオホイ兄弟、パオ兄弟
以下の組織は、四川省と長江流域の格老匯法格格志山堂の組織構造 です。
- 忠義本殿(「山、殿、水、香り」の四文字)
- 内八殿(内八殿はいずれも王朝の「都官」や閣僚)
- 「聖殿」の叔父とも呼ばれる香道長、香道を開くときに香を手にする人が客人です。
- 同盟証明書、または「中殿」の叔父、香殿を開くときに誓いを立てる人がゲスト牧師です。
- 「左首相」としても知られる叔父は広間に座って村の政務を担当している。
- 館に同行し、村の政務を補佐する「右宰相」とも呼ばれる。
- グアンタンは「将軍閣僚」の叔父としても知られ、人事の昇進、賞罰を担当します。
- 「尚書」としても知られる最高経営責任者は、人材の組織と訓練に責任を負います。
- 講堂。「ドンゲ」とも呼ばれ、叔父が礼儀作法を教育する責任があります。
- シンタンは「シゲ」としても知られ、叔父は刑法を担当しています。
- シールプロテクター
- 剣の鍔
- ワイバタン(ワイバタンは「軍隊」であり「支部」です)
- 腹心、「懲罰の代理」、叔父であり指導的な将軍。
- 賢者; 「賢者」の第二マスター、軍事顧問、企画(企画)担当。
- 恒侯(ヘンホウ) 家を管理する3番目の主人で、財政、食事、給与などの内務を担当し、赤い服を着て花を生けることも担当します。
- ジンフェン; 「ジンフェン」の四番目の妹。
- Steward; 「Steward」は対外および総務を担当する 5 番目のマスターで、事業、法執行、赤旗、青旗、黒旗、青港に分かれています。
- 巡視;「華関」六代目師範が巡視を担当し、内部巡視、外部巡視、山城(広口)に分かれる。
- インフェン; 「インフェン」の7番目の妹。
- Xian Pai; 「Xian Pai」は功罪を登録し、他人のために執り成すために使用され、白衣と8つの徳に分けられます。
- 江口; 「江口」 九業の正式名は、新人や昇任者を育成するために寺院を設立し、口をチェックする、口を揺さぶる、口を守ることに分かれています。
- モマン; 「モマン」の叔父、または「元門」、雑務を担当する兵士は、一般のモマン、法執行機関のモマン、元門、大男、小男、大男、小男、銅メダル、鉄印に分けられます。
- 「シャオバオ」または「タイバオ」とも呼ばれるシャオバオは、組織内での階級は半分に過ぎず、メンバーは通常、最初に社会に登録され、組織内で仁義を実践します。
トライアド
以下は珠江流域と南東部沿岸地域の三合会の組織構造であり、地理的関係は南陽地域の官公庁やギルドと比較的似ています。
- リーダー (489) は、「座っている人」または「話す人」としても知られ、社会全体の最高のリーダーです。
- 第 2 路元帥 (438)、別名「香師、先駆者」。通常は各ホールの入り口に 1 人以上がいます。第 2 路元帥はホールに座っていない限り権限を持ちません。
- レッド スティック (426) は通称「フィットマン」[注 1]と呼ばれ、そのほとんどが金メダルを獲得しており、426 の中で最も優れた選手は「礼儀正しさ」を意味するダブルフラワー レッド スティックとして崇められています。そして軍事的誠実さの才能。
- ホワイト ペーパー ファン (415)、「ミスター」および「ホワイト ファン」とも呼ばれます。事務業務、数学の指導を担当し、クラブの財務、統計帳の管理、およびクラブの軍事顧問も担当します。
- わらじ(432)は「鉄板」とも呼ばれ、九底(九底以上を一般に大底といいます)と呼ばれます。 「メッセンジャー」として内外との連絡を担当。
- 四十九(フォーティナイン)、別名「馬」(紅門式典開始時の馬集め)、入会式後に入会する人は四十九であり、一般会員である。
- 時主は「主主」とも呼ばれ、通常は会の財務やデータブックの管理などを担当する事務職であり、「白書ファン」と兼務することが多い。
- 式典を経ずにクラブへの入会を希望する非公式会員全員に青い提灯を吊るします。
南陽秘密結社党
以下は、シンガポール・マレーシア華人民間協会の当事者、企業、事務所の組織構造です。
- ビッグ・ブラザー: シンガポールとマレーシアの民間政党会社では「首相、元帥」とも呼ばれ、いずれも指導者を指し、党の精神的な象徴です。
- 二番目の兄と三番目の兄は、民間の党会社の副リーダーとアシスタントリーダーです。長兄、次兄、三兄の下に、それぞれ白扇、財務副官、虎将(先駆者)などを率いています。
- 卿: 紳士はパスワード、詩、エチケットに精通している必要があり、通常は年長であり、特定の会社に属しておらず、入学式を主宰する場合にのみ出席するよう招待されます。
- レッドスティック:「裁判官」とみなされ、氏のように特定の会社に所属せず、当事者間で紛争が生じた場合の仲裁人としてのみ機能します。
- ホワイト・ファン: 各党の芳香館の戦略家および指導者は、指揮官を派遣し、対外交渉で党を代表し、内政を処理する権限を持っています。
- 財務副官: 党の財政管理を担当する財務副官の多くは長兄またはバイ・ファンが兼任する。大きな組織の場合は、ロッカー (会計士) やロッカー (レジ係) などの専門職の称号もあります。
- タイガー ジェネラル: 「先駆者」 (ダ ボ ゴンなど) としても知られる彼は、領土を維持するために軍隊を率いたり、料金を徴収したりする責任を負う、党の凶悪犯で小さなリーダーです。
- 麦わら靴: 「鉄板」としても知られる彼は、党内の「メッセンジャー」の小さなリーダーとして機能し、諜報メッセージや命令を伝え、軍隊を率いて任務を遂行する責任を負います。
- 馬載:一般会員の中で最も多い。より上級で、新しい人を会員に引き入れることができる人は、「老馬」または「連れ馬」と呼ばれます。
天地恵
伝統的な天帝会には通常、長兄と師父(軍事顧問)の二つの称号しかなく、儀式を行う者が長兄であり、儀式に精通している人が師長となる。労働と専門職の肩書はますます詳細になります。ただし、設立時期や設立場所が異なると、同じ職名であっても意味が異なり、「氏」と「香主」は職名は異なるものの、立場や地位が似ている場合もよく見られます。しかし、天地が成熟期に達すると、一般に「三花迪」(八重の龍眼、一重の牡丹、二重の鳳凰の花を総称して「三花迪」と呼ばれる)主要な位置は3つだけになります。彼らの立場には次のような共通の特徴があり、それぞれ権力の「棒」、戦略の「扇」、行動の「靴」を象徴しています。
- ホンゴン(426、地上 12 枝)は最高司令官、炉の所有者、首相であり、舞台を開いてすべての事柄を統括する責任があります。
- 紙扇(415、十天茎)は軍事顧問、医師、学問の達人であり、軍事力、金銭、食糧を担当します。
- わらじ(432、第 9 宮殿) は将軍や指導者を導き、礼儀と軍事戦略の特徴を持ち、情報を伝え、命令を伝え、任務を遂行します。
3 つの主要な「パッシング」義務の下に次のようなものがあります。
- 会員(四十九、三十六天港、陰十八、陽十八、四十九点)は一般会員及び兵士である。
また、後に「役職はあるけど役職がない」という象徴的な役職は、特定の機会(開会式など)にのみ現れる、いわゆる「舞台上にはあるけど役職がない」ということが導き出されました。ステージの外には誰もいません」というもので、おおよそ次のとおりです。
会議録(広東三合会の海の下)
組織の極秘会員名簿は組織のトップのみが所有するもの。内容としては、組織結成の歴史、現在の組織一覧、構成構成、会員形態、宣誓、組織違反に対する刑法、暗記(隠蔽)言語、手話、組織の一員として公の場で表現する方法などが含まれる。場所。専門用語では「海の下」、「金は交換できない」とも呼ばれます。
石朗が台湾を攻撃したとき(1683年)、鄭克祥は祖父の鄭成功が金台山に設立し教会(明元堂)を設立した紅門天帝会に関する文書、名簿、印章などを鉄の箱に入れて封印した。そして海の底に沈んでしまいました。
トライアド協会の本
中華民国の紅門の会員、范松福はかつて次のような記事を書いた。1848年(道光28年、166年後、太平天国の初期段階)、永寧の郭永台が中山山を開き、福建省の漁師から入手した『金台山記』から「海の底」という意味で名付けられました。未来のトライアド会議の本はこれから発展しました。
遺跡と歴史的研究
『紅門志』陶庭図は、「鄭成功は台湾を掌握し、漢人移民の組織化を推進し、山を建立して堂を建て、金台山、明倫堂と名付け、蔡徳忠、方大紅、胡徳迪、馬を派遣した」と述べている。朝興、李世凱など、中原に向かって発展した「金台山」明倫堂は最初の山岳教会であり、その基本原則は次のとおりです。
彼は文武両面で優れた人物である鄭成功と協力し、漢王朝を建国し 、彼の軍隊が清軍と勇敢に戦いました。金台山堂の指導者が設立され、 軍は仁義の同盟を誓い、漢王朝を維持するために協力した。
多大な影響力
紅秀全は広西チワン族自治 区金田村で清朝に反逆する軍隊を起こし、その軍隊は太平天国軍と呼ばれ、太平天国を建国しました。
孫文はホノルルにいたときに革命活動に参加し、三合会の指導者から三合会に紹介され、山堂を設立し、自公堂を再組織し、興中協会を設立しました。 「コンチネンタルマウンテン」と名付けられました。孫文の『孫文学論』には次のように書かれています。「…康熙の時代までに、清朝は最盛期に達し、明朝の忠誠者も全員死亡した。生き残った2、3人の長老たちは、次のように述べています。事態は終わって取り返しのつかないことになったので、ナショナリズムを利用してそのルーツを後世に伝えたいということで、清朝に抵抗し、明朝を再興することを目的として団体を結成し、それを財産として利用しようとしたのです。後世の人々、これがホンメンの本来の意図だった。」
- 第二次世界大戦後、三合会は香港の犯罪組織に発展した。
その他の影響
- 台湾の清朝時代、朱儀貴は康熙 60 年 (1721 年) に反乱を起こし、紅門の助けにより7 日間で台湾全土を占領しました。
- 乾隆帝の治世(1711年~1799年)中、福建省莆田市と福清市の天帝会の指導者である万帝渓(万帝、万雲龍、雲龍僧、ホン二僧とも呼ばれる)に関わる事件があった。乾隆26年に創建されたと言われています)。
- 台湾では、福建省天地会の林双文(1787年)や戴朝春(1862年)などの反清武装事件に端を発している。
- 1855年、両国が国家となった際に李文毛事件が発生した。
- 清の時代、長期にわたる政府の弾圧にも関わらず、台湾の人々は密かに天地会を伝え続けた。現在、鹿港には福陵寺があり、清朝に対する林双文の反乱のために特別に設立されました。その主神は、林双文の平海将軍「王勲」です。また、台中県沙鹿市の「復興宮」では、林双文の変の際に「反清・復明」を誇示した九龍山の王勲を主神として崇拝し、お祀りしました。犠牲。
党(結社)と宗派
現代中国の秘密結社は、「教」と「会」の 2 つのカテゴリーに分類されます。「ティアオ」は宗教的信念を組み合わせたもので、中国北部で一般的に普及しています。主に中国南部で人気があります。天帝回の発祥の地である福建省の張と泉は、長年武器を使った戦いが盛んであった。田舎の人口の少ない苗字が別の苗字で団結して人口の多い大きな苗字に対抗するのが「異姓同盟」の社会的起源です。人口は清朝初期から乾隆時代にかけて大きく増加した。福建省と広東省東部には人口は多いが土地は少ない。乾隆帝の治世中期までに、土地を持たない農民が多数浮遊人口となった。彼らは全国の都市や町に集まり、小規模な商人、労働者、あるいは放浪者、失業した浮浪者として働きました。秘密結社への参加は、主に生活上の保護を求める必要性に基づいています。協会に参加する人々にはいくつかの理由があります。いじめを避けるために助け合い、ホームレスを集めて強盗をし、逮捕に抵抗し、身代金を求めて誘拐し、武器を持って戦い、復讐を求め、保護費を集めて協会を広めることによってお金を集めます。
清朝の乾隆時代には、紅門は何度も包囲され、乾隆は漢民族を重用し、広興文人刑務所を設け、大規模な反満州軍や文学団体の存続が困難となった。代わりに、地域社会や組織が登場しました。
1911 年の革命の初めに、革命家たちは三合会が「清王朝に対抗し、明王朝を復興する」ために設立されたものであり、それは政治的必要性に基づいていると述べた。国内の回族政党と海外の華僑の支持を得る必要があるため、協力できる回族政党はすべて紅門組織とみなされます。なぜなら当時の回党は海外からの経済支援も相まって、既製の強力な組織だったからである。同盟は「革命的な小隊編成」を呼びかけるだろう。
清朝時代の秘密の言葉には、「瓶がいっぱいになったら水を抜く必要がある。葉は緑、花は赤、蓮根は白い」というものがあるが、これは「満州族の清朝に反対した暴力団には緑人が含まれていた」という意味である。 「紅門派、紅門派、白蓮宗」という諺もありますが、「紅花、緑葉、白蓮根(紅門派、青崗派、白蓮宗のこと)」という言葉もあり、この三派はもともとある家庭。"
白蓮宗
白蓮宗は南宋時代に初めて現れました。清朝中期、耕作地の不足と農民の出産と子育ての困難のため、白蓮宗は四川省、陝西省、湖北省の清朝の地方政府に農具を使って抵抗したと主張した。 「神聖な戦いに熟達し、武器や弾丸に対して無敵である」ため、清政府は彼らを白門教団と呼び、後期には東南アジアに発展した。 「二思赤宮」「二思老君」とも呼ばれる。長い間、紅門の勢力範囲は拡大し続け、白門は多くの信者が私的に紅門に加わった末期を迎えている。
青港と紅門
対立を避けるため、両宗派は依然として自らを「清紅家」と呼んでおり、いわゆる「紅門、青崗、白蓮の根」の三宗教は本来一つである。家族。"特に革命党の思想が隆盛を極めた清朝末期には、多くの青年団弟子も清朝に反対するようになり、両派間の敵対関係は徐々に薄れていった。
神様を祀る会
1843 年に洪秀全によって設立され、太平天国の前身であり、天帝会衆も参加しました。
広東三合会
台湾での林双文の蜂起後、天地協会は清朝の法律で明示的に禁止され、指導者とそれに参加する意欲のある人々は全員処刑される予定だった。政府の調査を避けるために、彼らは名前を「スリーポイント協会」と「トライアド協会」に変更しました。道光治世 10 年(1830 年)、彼はこの事件の際に劉光三の追悼文を書き、次のように述べている:「人民に最も害をなす広東の山賊には 3 つのポイントがある。諺にあるように、彼らはすべきである」話すときは決して自分たちのルーツを逸脱してはならず、手を挙げるときも決してその 3 つのポイントから逸脱してはなりません。広東省東部の原住民は誰もが知っています。」当時の広東省では三合会社会が広く普及していたことが分かる。 1848 年以降、福建省の漁師が海底で発見したという三合会書(紅門会書)の伝説が残されました。
太平天国の乱(1851 年) の後、広東省と広西チワン族自治区の紅門組織は互いに連絡を取り合い、同盟を結び、三合会を組織しました。彼らは広東省と広西チワン族自治区で大衆運動を開始するために瓊華ギルドホールの赤い船で会合を開きました。広州や佛山などの大都市では)、ホンビンを訓練するために武術グループに唐口が設立されました。
1854年、太平天国が金陵に首都を置いたことを知った後、李文茂と紅冰、三合会グループが反乱を起こし、清朝は瓊華ギルドホールとすべての紅船を焼き払った。その後、三合会は、当時のさまざまな南泉宗派はすべて福建省少林寺の少林寺五老から派生したものであるとして、南少林寺を焼き払ったという伝説を広めました。その目的は、もともとバラバラだった武術グループを組織することでした。清朝と共同で戦う。
広東・広西三合会は次のように記録している:「当時、(南部)少林寺の武術は非常に強かったので、清王朝は嫉妬していた。彼らは軍隊を送り込んで一斉攻撃したが、攻撃できなかった。」陳氏新しいチャンピオンであるウェンウェイは好意を寄せ、アドバイスを提供し、寺院の僧侶である馬寧と共謀しようとし、内部と外部を団結させようとした子供たちと少林寺は破壊され、僧侶たちは散り散りになりました。宗禅師智山(ホン・クァンの指導者)、道士のパク・メイ(パク・メイ宗の指導者)、五梅師泰(詠春拳の創始者)、ミャオ・シェン(広州華)の5人。)そして馮道徳も逃げた。
フォームの背景
賈道時代、福建省、広東省、広西チワン族自治区などの人口は急激に増加し続け、破産した農民や浮遊人口も増え続け、秘密結社が発展する余地が多かった。清朝初期から道光まで、福建省の人口増加は12倍、広東省の人口増加は24倍、広西チワン族自治区の人口増加は30倍でした。流動人口と移民により、トライアドは福建省と広東省から広西チワン族自治区、貴州省、雲南省、江西省に広がった。道光時代、広西チワン族自治区には何百もの三合会があり、「兄貴のいない村はほとんどない」ほどに発展した。三合会は地元の山賊と団結し、同盟を結んで訪問し、盗作で生計を立てていた。あるいは、「集団訓練」やボディガードなどの名目で、さまざまな業種から現地みかじめ料を徴収することもある。
アヘン戦争の 10 年前、道光 11 年 (1831 年) には、三合会が中国南部の 5 ~ 6 省に広がり、無数の人々がいて、役人や兵士のほとんどが三合会であったという報告があり、頻繁に殺人が行われていました。トライアド関連。
林則徐は、1839 年の虎門でのアヘン撲滅とアヘン戦争への報復として、イギリス軍が軍艦を使って広東を攻撃するだろうということを知っていたため、すでに広東省のさまざまな鎮や町、特に三江流域と三江流域で民兵組織を組織していた。海岸、沿岸警備隊を駐屯させる。
1843 年に南京条約が締結された後、貿易のために5 つの港が開かれ、イギリスは広州に入る権利を持ちました。広東市の貴族や民衆は断固として反対し、野蛮人が市に入ってきたら太鼓で攻撃するだろうと述べた。皇帝の遺言に従い、斉英は締結された国際条約を遵守し、英国との平和を維持した。国際情勢に無知で無知だった原住民の怒りは満州族と清族の地方政府に向けられた。かつて彼らはナイフや武器で武装した数千人の人々を集め、知事のヤメンを焼き払った。
五港貿易の後、広東省は対外貿易の独占を失い、経済は衰退し、失業者の数は大幅に増加した。戦時中、広東各地で林澤忠が設立した民兵組織は落伍者と化し、三合会の温床となった。三合会および他の宗派は広東省と広西チワン族自治区で急速に成長し、太平天国の乱を含む反乱を続けました。 1854 年、広東省と広西チワン族自治区のさまざまな三合会が同時に反乱を起こし、大城王国を設立しました。当時の紅門人のほとんどは広東省の三江流域の出身でした。大成王国は指導者を失い、広州市の占領に失敗し、葉明チェンによって次々と敗北し、紅門の弟子たちを虐殺しました。イギリス軍とフランス軍が広州に侵攻したとき、葉明チェンは民間連隊訓練の利用を主張しなかった。
イギリスはエルギンを派遣してフランス軍と協力し、1857年12月中旬に広州占領戦争を開始した。葉明チェンはイギリス軍とフランス軍が陸上から攻撃することはなく、防衛する計画もないと信じていた。南海、番禺のあらゆる分野から地元の英雄を募集するという提案を無視すると、広州市はすぐに倒れた。それどころか、イギリス軍は途中のさまざまな町から来た勇敢な兵士たちによる自発的な抵抗に遭遇しました。広州は12月29日に陥落した。英国とフランスは、満州族役人の白桂氏の復帰を監督する委員会を設置した。白桂が広州を統治していた時代、イギリス軍は多くの連隊訓練施設を襲撃したが、この動きにより、各地の町や村の紅門住民の清朝廷とイギリスに対する不満が高まった。
1858年にイギリス軍が市内に入ると、関係団体や政党は自らを守るために三合会の地下活動に参加し、後に革命党に加わった。
上海広東港-リトルナイフクラブ
1849 年、砂糖、茶、絹の商いに従事していた香山出身の劉立川が上海に来て、村民の仲間で広照協会を設立しました。彼は有名なシャオダオ協会のリーダーでした。当時、香山族は広兆族の中で最大の民族で、その数は2万人を超えていた。小道匯の蜂起が失敗した後、清政府によって焼き払われました。広東省の暴力団が上海に導入されたことがわかる。
他の
天地協会は広く普及しており、他にも「清水協会」「短剣協会」 「格老協会」「双剣協会」「リトルナイフ協会」「赤旗協会」などがあります。 Jianzi Society」、「Bagua Society 」、「 Tim Brother Club」、「Triad Club」、「Chi Kung Tong」、「Red Gang」、Pao Ge Club、Red Spear Club、Huang Sha Clubなど の名前。
太陽と月の出会い
太陽も月も明るい
満州紅門回党
三民主義のナショナリズムに関する第 3 回講義で、孫文は次のような記事の例を挙げました。
それによると、紅門回党は王党派になって満州皇帝を守るために行ったのであって、もともと清王朝と戦って明王朝を再興した紅門回党ではないということだ。
Sun Wen はさらに次の一節を続けました。
それによると、紅門馬頭はすでに左宗棠によって破壊されており、孫文が革命を起こそうとしたときは代理店がなかったという。孫文は、正統的な中国の「先祖伝来のヘルオ」ナショナリズムがタタール人の混血によってずっと前に敗北していたことを証明するために2つの例を挙げた。
小説における紅門天地協会
見る
コメント
参考文献
研究参考文献
- 秦宝奇著、福州の紅門の歴史、福建人民出版社、2012年。
- 秦宝奇著、福州の真実の歴史、福建人民出版社、2000年。
- 胡朱生著、瀋陽人民出版社、ISBN 9787205034290。
- 荘継発、台北における天地会の起源に関する調査:国立故宮博物院、1981年。
- デビッド・オウンビー著、リウ・ピン訳:「同胞団と秘密のパーティー」(北京:商務新聞社、2009年)。
- 三谷隆著、李恩民他訳『秘密結社と中国革命』(北京:中国社会科学出版社、2002年)。
- Mu Dian: 「西洋の学者による天地会の研究の簡単な要約」。






















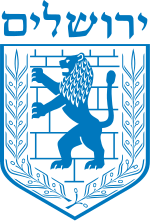


















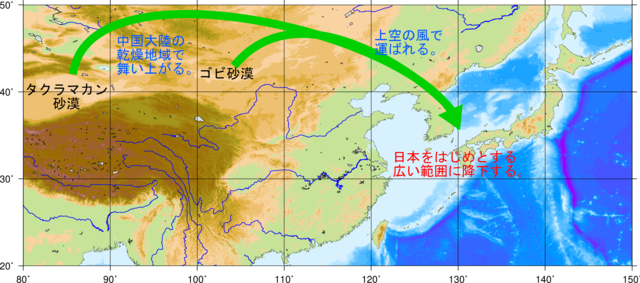
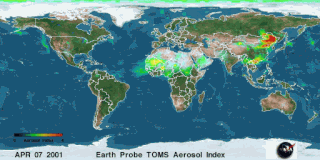
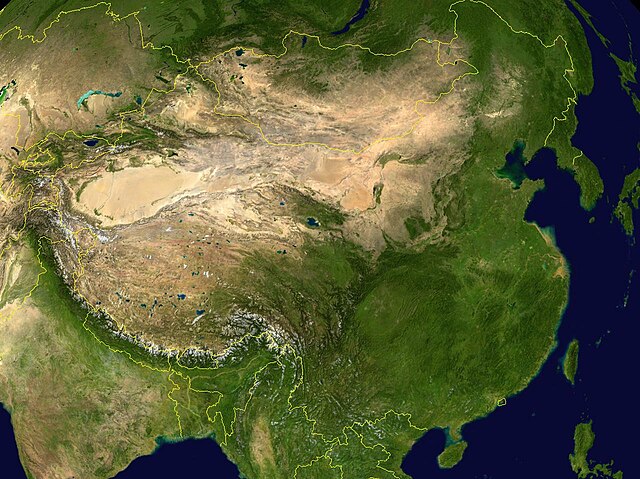
![X.Y. Zhang, et al.(2003)による黄砂発生源の分布地図[19]。タクラマカン、ゴビ、黄土高原が大きな割合を占めるが、周辺の砂漠からの発生もある。](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Asian_dust_sources_map.svg/640px-Asian_dust_sources_map.svg.png)